ナミを初めて見たときの衝撃は、今でもはっきりと覚えています。あれは小雨が降る六月の午後のことでした。ユストは知人の紹介で、地方の豪族が経営している小さな牧場を訪れました。この時、ユストは馬を一頭、所有していましたが、既に8歳を超えており、戦場に連れていくは少し年を取っていました。
しかし、急いで新しい馬を買うつもりはなく、時間を掛けて納得がいくまで探そうと思っていました。言い換えれば、馬というのはそれほど大きな買い物なのでした。
雨に煙る納屋の横を通りながら、ユストはぼんやりと良い馬がいるといいなと考えていました。
ユストたちが厩舎に入ると、あちこちからブルルルという鼻息が聞こえてきました。厩舎の中には、十頭ほどの馬がいました。厩舎に足を踏み入れた途端、ユストは心が躍りました。一番、手前にいる馬でさえ、相当な名馬なのです。それが厩舎の奥にいくにしたがって、どんどんレベルが上がっていくのです。この状況で、目移りするなというほうが無理です。
薄暗い厩舎の中を奥へ進んで行くと、一番奥に何か光るものがいました。それがナミでした。馬から放たれる強い気、明るく生き生きとした瞳、光沢のある肌、滑らかに隆起した筋肉、美しいたてがみ、それらのすべてが相まって、ユストの目には本当にその馬が光を放っているように見えました。
ユストが馬房に近づいていくと、青毛*の馬はじっとユストを見つめました。肩の車骨の幅は広く、四足は麻を立てたようにまっすぐでした。このように、足をまっすぐにして立てる馬は稀です。多くの馬は、脚が多少は前後に傾いているものです。ユストは一目で、この馬が類稀なる駿馬であることを見てとりました。
* 馬や獣の毛色の名。 つやのある黒色で、青みを帯びて見えるためにいう。
青毛の馬と目が合った途端、ユストは雷に打たれたようにその場から動けなくなってしまいました。馬の目には強い光が宿っていましたが、一方で落ち着いた色も湛えており、それがこの馬が悍馬*でもなければ、臆病な馬でもないことを示していました。
迷いや逡巡は一瞬にしてどこかへ飛んでいきました。
――この馬が欲しい。この馬でなければ駄目だ。
この機会を逃したら一生、後悔するという予感がしました。間違いなくこの馬は一生に一度出会えるか、出会えないかくらいの駿馬です。
一方、ナミもまた、ユストからまったく視線を逸らすことなく、ユストをじっと見つめていました。
――何を考えているのだろう…
後に、万人をして、人馬一体とまで言わしめるほどのコンビとなる一人と一頭でしたが、この時はまだ互いのことをよく知りませんでした。
ユストがそっと手を伸ばすと、馬はユストの手の平の匂いを嗅ぎ、少しだけ考える素振りを見せました。
――俺のことを気に入ってくれたようだ。まずは第一段階突破か…
乗馬の名手であるユストは、乗り手と馬の相性がいかに大切であるかを痛いほど知っていました。
「ホホホホ。この馬がお気に召されましたかな?さすがはユスト様、お目が高いですな。馬のほうも、貴方を気に入ったようだ。」
ユストが振り返ると、少し離れた所から見守っていた牧場の主が音もなく近づいてきました。老人は枯れ枝のように細く、ほとんど体重がないようで、歩くときもまったくといっていいほど音を立てませんでした。
「この馬をご覧なさい。まるで、やっと本当の主人に巡り逢えたというような顔をしておる。この馬も相当あなたを気に入っとりますぞ。」
相思相愛ですなと言って、老人はホホホホと笑いました。
「そうでしょうか?」
ユストが問いかけると、小柄な老人は頷きました。
「この馬は、非常に利口でしてね――」
老人が愛しそうに馬の鼻づらをなでると、馬は甘えるように顔をすり寄せました。老人は隠居後の人生をすべてを馬の育成に奉げてきましたが、その中でもこの馬は特別でした。手塩にかけて育てた馬を手放すのは、大切な娘を嫁に出すようで辛いのですが――もっとも、この人には娘はおりませんでしたが――良い主人に巡り逢えたとなれば、喜んで送り出さねばなりません。
一事が万事、そんな調子でしたので、老人は「相応の買い手が現れなければ、一生、この馬を自分の手元に置いておこう」と密かに思い定めていました。そこへ、ユストが現れたのです。これを運命と言わずして、何と言いましょう。馬自身もユストに不満はないようですし、老人としてもユストが買い手であれば喜んで手放せる気がしました。
「この馬は子供や小さな生き物にはとても優しいのですが、大人の男が相手ですと厳しい態度をとることがあります。」
老人は苦笑いを浮かべると、こう続けました。
「当家には三人の息子がおりますが、末の息子がとんでもない放蕩息子でして。いやはや、まったく、私の教育が悪かったのでございますが…。年をとってからできた子でしたので、ついつい甘やかして育ててしまいました。」
老人は言い訳のように呟くと、目を細めました。
「その息子がこれに乗りますと、それはもう、傍で見ていても可笑しいくらい嫌がるのでございます。それが、長男が乗りますというと――長男というのは真面目なだけが取り柄の男なのですが――急に大人しくなるのでございますから困ったものです。」
困ったと口では言いつつも、老人はさほど困ったふうでもなく笑ってみせました。
この人は最下層から身を起こした人物なだけに、人を見る目は確かでした。老人の好意に溢れる視線を受けて、ユストは控えめに微笑み返しました。
――そうであれば、本当に良いのだが……そうとなると、あとは値段の問題だけだな。私に買える値段であれば良いのだが… おお、神よ。どうか私に味方してください。
ユストは心の中で呟きました。
* 悍馬: 悍馬:気性が荒く、制御しにくい馬。あばれ馬。荒馬。
数十分後、肩を落としたユストは、尚も馬の前から離れられずにいました。馬の値段はユストの予想を遥かに上回るものでした。しかも、老人は一円たりとも値引きしないと言うのです。
――高いだろうとは思っていたが、まさかこれほどとは…
どうあがいてもユストの年俸で買えるような額ではありませんでした。このとき、ユストは二十二歳。実力で一万人の長にまで登りつめていましたが、スクエアードでは年功序列が厳然として根強かったため、どれだけ活躍をしても、若年のユストの年俸は微々たるものでした。
老人が値下げに応じなかった理由の一つは、老人がこの馬の価値を固く信じて疑わなかったことにあります。この馬を老人は「羊のようでもあり、獅子のようでもある」と評しました。ユストは老人の言葉の意味をすぐに理解できましたが、本当の意味でその言葉を理解するのはもっと後のことになります。
これは余談ですが、後日、再び牧場を訪れたユストはこの馬を最初から難なく乗りこなして、改めて老人を驚かせることになります。
そして、人が値下げを拒んだもう一つの理由は、ユストにどれくらいの覚悟があるか確かめるためでした。特別な馬を維持するには、特別な環境、世話、熱意、そして金が必要です。農耕馬が経済的な小型車だとしたら、サラブレッドは桁違いのお金が掛かるF1カーです。老人はユストにそれだけの犠牲を払う覚悟があるかどうか試したのでした。
ユストは後ろ髪を引かれる思いで、厩舎を後にしました。ユストの背中に向かって、青毛の馬は戻ってこいとでも言うようにカッ、カッと床を蹴りました。
――振り返るな。
ユストは自分にそう言い聞かせました。
――俺には過ぎた馬だ…
立ち去るユストの後ろ姿を、黒い二つの瞳がずっと見詰めていました。
――人が馬を選ぶのではない。馬が人を選ぶのだ。
背中に強く突き刺さる視線に、ユストは足を絡め取られるような錯覚さえ覚えました。
厩舎を出たユストは、蕭々と降る雨の中、胴震いをしました。
その夜、ユストはベッドに入ってもなかなか眠ることができませんでした。あの馬の姿が瞼に焼き付いて離れないのです。何度も寝返りを繰り返した後、ユストは溜息をついて起き上がりました。
時計の針は零時を回っていました。しかし、ユストはどうしても今からモルデカイに会うべきだと、感じてなりませんでした。モルデカイに相談したところで、どうにかなるとは思えませんでしたが、話を聞いてもらえば少しは気が晴れるかもしれません。
少し躊躇った後、ユストは服を着替えると、モルデカイの家へと向かいました。モルデカイの家は近衛兵の宿舎から歩いて三十分ほどのところにありました。
宿舎には門限がありましたが、ユストは立場上、緊急で呼び出されることも多かったため、門番に咎められることはありませんでした。
三十分後、モルデカイの家の玄関を遠慮がちにノックすると、モルデカイはまだ起きていたらしく、気持ち良くユストを迎え入れてくれました。
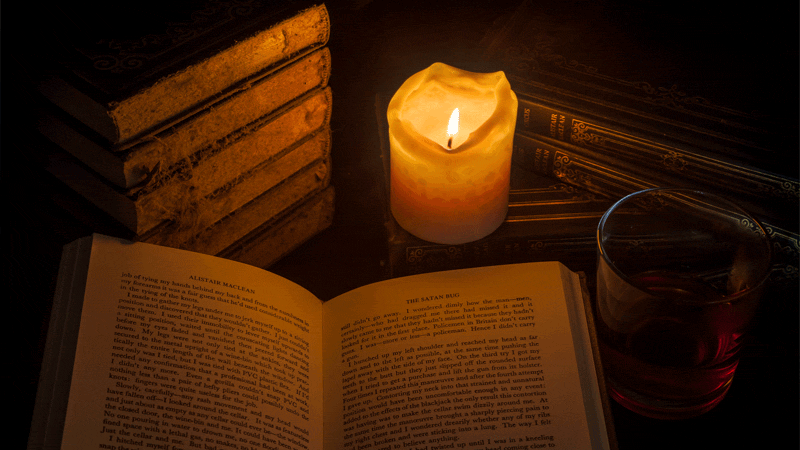
ユストはモルデカイに今日、見てきたことを少しずつ話し始めました。ある牧場で素晴らしい馬を見つけたこと。しかし、値段が高くて手が出ないこと。頭では諦めるべきだとわかっているのに、どうしても諦め切れないこと、等々。
黙って聞いていたモルデカイは、ユストの話しが終わると静かに立ち上がり、奥へと引っ込みました。そして、しばらくすると、黒い箱を手に戻ってきました。箱には何重にも鍵が掛けられていました。
モルデカイは懐から鍵の束を取り出すと、鍵を一つ一つ開けていきました。箱の中には、何やら重そうな袋が入っています。モルデカイがゆっくりと袋を開けると、中からは数えきれないほどの金貨が出てきました。
ユストは驚きました。ずっと貧乏だとばかり思っていた養父が、このような大金を持っていようとは夢にも思わなかったからです。
「息子よ。」
モルデカイは、ユストに呼び掛けました。モルデカイに息子と呼ばれたのは、これが二度目でした。一度目は「跡を継いで文官になるのではなく、軍人になりたい」と打ち明けたときでした。そして二度目が今日です。
「息子よ。将たる者は良い馬に乗らなければならない。良い馬に乗れば、それだけ生き残る確率が高くなる。将の使命は兵を統率することだけでない。兵を生きて国に連れて帰ることも、将の使命である。将が倒れてしまったら、残された兵はどうなるのか。壊滅するより他ないではないか。だから息子よ、よく聞くがよい。これはお前のために出す金ではない。何千、何万という兵士たち、延いては、その兵士の家族のために出す金である。」
ユストはモルデカイに黙って頭を下げました。この金貨はモルデカイが長年にわたってコツコツと貯めてきたものに違いありません。長年、モルデカイと一緒に暮らしてきたユストは、モルデカイが粗食を常とし、一年を通して夏服と冬服を二着ずつしか持っていないことを知っていました。ユストは何かを言おうとしましたが、胸が詰まって言葉になりませんでした。
モルデカイはユストが子供のうちから、仁と義について根気強く教えてきました。今日のことは、その教育の集大成と言っても過言ではありません。
全財産を少しも躊躇うことなく差し出すことによって、モルデカイはユストに将として心構え、究極的には人としてのあり方を示そうとしたのです。モルデカイは文官でしたが、古今東西の歴史書を読み漁り、ありとあらゆる戦法を研究していました。ユストも何度か、モルデカイの的確なアドバイスに命を救われたことがあります。モルデカイには実戦経験がまったくないことを鑑みると、これは驚くべきことでした。
ナミという素晴らしい馬を得て以来、ユストとナミは常に一緒です。戦場でナミに命を助けられたことは数知れず。ナミによって大勢の兵士の命も救われてきたことは、言うまでもありません。ユストは身をもって、モルデカイの教えの正しさを証明してきました。
一方、ナミも老人の言葉の正しさも、身をもって証明してきました。
ナミは平素は羊のように柔順でしたが、戦場では一変、獅子のように猛々しくなりました。自分と主人に危害を加えようとする者に対しては容赦がなく、踏み潰すことさえも躊躇いませんでした。
軍馬は火煙や大砲、阿鼻叫喚にも怖じけることがない気の強さがなければなりません。一方で、人間の命令に従う従順さも必要です。また、重い鎧を着た騎士を乗せて戦場を走り回れるだけの体の大きさと体力も必要でした。馬が大きければ大きいほど、上の乗っている人間は戦いにおいて有利になります。
ユストがナミを手に入れた頃から、「スクエアードに智、勇、胆を備えた名将あり」との噂が広がり始めました。事実、黒馬に乗ったユストが戦場に姿を現すと、それを見ただけで敵兵は恐れ戦き、潮が引くよう後退しました。
モルデカイの深慮によって、ユストはかけがえのない戦友を手に入れたのでした。
あとがき
小さい読者の皆さん、今回はちょっと難しい言葉が多くなってしまいました。ごめんなさい。わからない言葉は、お母さんやお父さんに聞いてくださいね。
歴史小説好きの方の中にはお気づきになられた方もいらっしゃるかもしれませんが、このお話は司馬遼太郎先生の「功名が辻」から着想を得ています。
「功名が辻」の主人公は、武将の山之内一豊ではなく、妻の千代です。千代が内助の功を発揮して、貧乏大名の一豊に名馬を買わせた話は、明治から昭和の初期にかけて、どの国語の教科書にも載っていたくらい有名な話だったらしいです。現代の教科書でいうところの、「蜘蛛の糸」的な扱いだったのかもしれません。
ドラ赤の中では、モルデカイは王の相談役を務めているエリート官僚という設定です。
しかし、高価な本をたくさん買いまくっているために、あまり贅沢はできないのです。それが子供だったユストの目には「貧乏」と映ったのでしょう。







コメント